ページID:13818
更新日:2025年10月28日
ここから本文です。
貝毒・テトラミン〔貝〕
貝毒とは
貝毒は,ある種のプランクトンが作り出す毒です。ホタテガイやカキなどの二枚貝がこの有毒化したプランクトンをエサとして食べることにより,貝の体内に毒が濃縮・蓄積してしまいます。その結果,本来無毒である二枚貝が毒化してしまうのです。
麻痺性貝毒の特徴
東北地方では初春から秋にかけて発生することが多く,食べるとフグ中毒に似た食中毒を起こすことがあります。
原因プランクトン
アレキサンドリウム属等
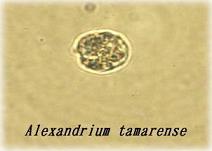
主な症状
しびれ,麻痺,重症の場合は呼吸麻痺で死亡
潜伏時間
30分~4時間
毒量の基準
体重20gのマウスを15分間で死亡させる毒量を1マウスユニット(MU)とする。
出荷規制値
可食部1g当たり4MUを超えるもの
毒の性質
熱に対して安定で水に溶けやすい。加熱調理しても分解されない。
※麻痺性貝毒の食中毒発症量は3,000MU以上と言われている。
下痢性貝毒の特徴
この貝毒の原因となる有毒プランクトンの発生は,暖流の影響を受けやすく,主に初夏にかけて発生します。食べると下痢を主な主症状とした食中毒を起こすことがあります。
原因プランクトン
ジノフィシス属,プロロセントラム属等
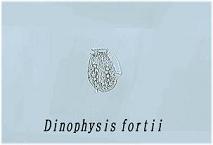
主な症状
下痢,悪心,嘔吐,腹痛
潜伏時間
食後1~2時間で発症することが多い
毒量の基準
オカダ酸、ジノフィシストキシン-1及びジノフィシストキシン-2並びにそれらのエステル化合物について、毒性等価係数を用いてオカダ酸当量に変換したものの総和
出荷規制値
可食部1kg当たり0.16mgオカダ酸当量を超えるもの
毒の性質
熱に対して安定で油に溶けやすい。加熱調理しても分解されない。
どうすればいいの?
毒化した貝類の流通防止対策として,生産地で定期的に貝の種類や海域別に毒性検査が行われています。この検査の結果,規制値を超えた場合は出荷規制措置がとられます。
また,ホタテガイでは,規制値を超えた場合でも認定施設で有毒部位を除去し,安全を確認した後で安全証紙を貼って出荷されています。以上のことから,店頭で毒化した貝が販売されることはありません。
但し,自分で採取した天然の二枚貝を食する場合は,関係機関が提供している貝毒情報等に注意する必要があります。(このホームページや仙台市食品監視センターでも情報提供しています。)
殻付きツブの食べ方知っていますか?
「ツブ」や「マツブ」という名称で流通している殻付きの巻き貝の仲間には,有毒な「だ液腺」を持っているものもあり,調理方法を間違うと食中毒の原因となります。「だ液腺」の正しい除去方法を覚えて,殻付きツブによる食中毒を防ぎましょう!
代表的な「殻付きツブ」

和名 ヒメエゾボラ
大きさ 11~12cm
色 紫褐色
特徴 らせん状に脈をめぐらし,コブ(矢印)を持つのが特徴。
※仙台市に入荷する殻付きツブのほとんどを占める。
有毒なだ液腺

【殻から取り出したむき身】
毒成分の分布
ヒメエゾボラ,エゾボラモドキなどのだ液腺中にはテトラミンという毒が含まれます。この毒は煮ても壊れません。だ液腺は,他の内臓と異なり肉の中にくい込んでいるため,除去されないまま食べられることが多く,しばしば食中毒の原因となります。
中毒症状
食後30分位で頭痛,吐き気,船酔い感を示し,視覚異常を呈しますが,回復は早く死亡例はありません。
だ液腺
だ液腺はピーナッツのような形をしており,生の時は半透明で柔らかく,ボイルすると図のように白色になり固くなります。

【取り出した「だ液腺」】
中毒最小量
貝の大きさ,貝の種類によっても異なりますが,ヒメエゾボラでは3~5個分のだ液腺,エゾボラモドキでは1個分のだ液腺でも症状が出ることがあります。
だ液腺除去方法
- (1)貝の身を取り出す

- (2)内臓と肉を切断する

- (3)貝のフタを下にして切り口を入れ開く

- (4)中から白色のだ液腺(2個)を取り出し,十分水洗いする

パンフレットダウンロード
関連リンク
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.




