ページID:11389
更新日:2016年9月20日
ここから本文です。
心の病気とは 2.病気について ~精神保健福祉ガイド はあとぺーじ
2.病気について-統合失調症を中心に-(1)
2-1.統合失調症とは特別な病気ですか?
統合失調症は、全世界で共通してみられる、心の病気の中でも重要なものです。多くは思春期や青年期に発症し、けっして稀な病気ではありません。一生のうちにこの病気にかかる人の数は、地域にもよりますが、約100人に1人と言われています。また、現在、我が国の全ての診療科に入院している人の数は約140万人ですが、その7分の1にあたる約20万人が、この病気のために入院して治療を受けています。つまり、この病気にかかっている人は大勢いるのです。
偏見や偏った報道によって、統合失調症をはじめとする精神障害者が不必要に危険視されることがありますが、犯罪白書などを見ても、精神障害者の犯罪率がそれ以外の人に比べて高いという根拠はありません。不幸にしてまれに起こる事件に注目が集まることがありますが、多くの人は地域で普通に暮らしている「一般市民」なのです。
むしろそうした偏見が、精神科への早めの受診を妨げていたり、病気や障害の受容を難しくしていたり、精神科の治療に対する意欲をそぐことになるなど、病気の早期発見や再発の防止を妨げていると言うこともできます。また、地域での社会復帰施設整備に対する反対等により社会資源の整備が進まず、支援があれば地域で暮らせる精神障害者がなかなか退院できず入院が長期化しやすいといった状況もあると言われています。
統合失調症は、以前は精神分裂病と呼ばれていました。しかしこの名称は「精神機能がバラバラに分裂して元に戻らない」という悲観的で人格否定的なイメージを与え、この病気に対する差別偏見を助長する弊害が大きかったのです。後に説明するように、この病気は実際には不治の病でもなければ、人格崩壊を免れない病気でもありません。そこで当事者や家族の団体からも呼称変更の強い要求が出ていました。これを受けて精神医学・医療の基幹学会である日本精神神経学会を中心として検討が進められ、2002年に統合失調症という新しい呼称が採択されたのです。その後早い時期に厚生労働省も公式の病名として認めたこともあって、新しい呼称は当事者、家族、医療関係者、そして一般市民の間にも普及しています。
本書ではこうした状況を踏まえて、すべての記載を「統合失調症」に統一しています。
2-2.どんな症状がありますか?
統合失調症の症状は人によってかなり異なった様子を見せますが、共通する部分も多いので診断の助けになります。また、病気の時期によって目立つ症状が異なるのも特徴です。
以下に典型的な症状をあげます。ここでは「陽性症状」と「陰性症状」という、広く使われている分類を用いて説明します。
陽性症状(急性期に多く、回復期~慢性期に残存することもある)
|
幻覚・・・・ |
その場にいないはずの人の声による悪口、噂話、命令などの「幻聴」が最も多い。他に「体感幻覚」と呼ばれる内臓などの奇妙な感覚や、「幻視」が出ることもある。 |
|---|---|
|
妄想・・・・ |
事実に反することを病的に確信する症状。周囲の人たちが意地悪やあてつけをする、自分を陥れるための陰謀がめぐらされている、盗聴、監視、尾行されているなどと思い込む「被害妄想」や、周囲の出来事を自分に関係づけする「関係妄想」が多い。 |
|
自我障害・・ |
自分と他人との心理的な境界があいまいになる症状。自分の行動や思考、感情が外部から操られる(操られ体験)、考える内容が外部にもれ伝わるなどの奇妙な体験をする。 |
|
思考の |
思考の意味脈絡がなくなり、会話していても何を言っているのか判りにくくなる。 |
|
興奮状態・・ |
本来であれば気にしないような些細な刺激に対して興奮したり、怒ったり、大声をあげたりする。 |
こうした陽性症状が強まるととても不安になり、夜も眠れず憔悴していきます。時には、妄想の対象となった人に苦情を訴えたりします。家族や知人からは、本人が症状によって体験している異常な世界の意味が理解しにくいことも多いのです。
陰性症状(回復期~慢性期に多い)
|
意欲低下・・ |
物事を始めたり続けようとする気力がわかない。朝も起きづらくなり、日中も何もせずに過ごしてしまうようになる。 |
|---|---|
|
感情の平板化 |
喜怒哀楽の感情がわかない。その場にふさわしい気持ちが感じられない。 |
|
自閉・・・・ |
人と付き合ったり会話したりするのを避け、自分の世界に閉じこもるようになる。 |
こうした陰性症状は、生活リズムの低下、対人関係の苦手、作業能率の低下として現れることが多く、家族からは怠けぐせがついただけのように誤解されることがあります。
開いてみよう
2-3.どんな経過をたどりますか?
身体の病気でも本格的に発症する前に、いろいろな前駆症状が出ることがありますが、統合失調症の場合も同じです。一般的には、不眠などの身体的不調や漠然とした不安や集中困難などといったもので、はじめは本人も家族も精神症状とは思わずに内科などを受診することもあります。再発の前にも同じような前駆症状が現れることがあるので、これを知っておくことは再発予防に役立ちます。
ストレスを減らすなどして前駆症状の段階で治まることもありますが、病気の勢いが止まらなければ、幻聴や妄想などの「陽性症状」を中心とした「急性期」に進みます。「陽性症状」が次第にやわらぐと、意欲、活動性の低下などの「陰性症状」を中心とした「回復期」に移ります。その後は時間をかけて完全な回復(寛解)に向かう場合もあり、さまざまな程度の障害を残す場合(慢性期)もあります。
それぞれの時期の長さには個人差があり、必ずしも典型的な経過をたどるとは限りません。「陽性症状」が長時間持続したり、重い障害のため入院の継続を余儀なくされる人もいますが、むしろ少数です。逆に、年をとってから障害が軽くなる人が少なくないことが近年の研究でわかってきています。
また、いったん回復しても再発しやすい面があることもこの病気の特徴ですので、再発予防が大きなポイントになります。
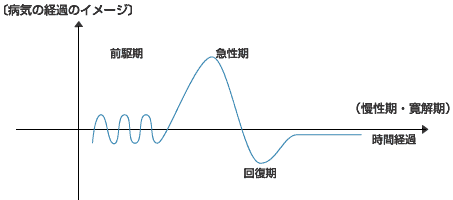
開いてみよう
2-4.急性期に神経が過敏になると、どんな状態になるのですか?
急性期に神経が過敏になると、情報を処理する上での障害が現れます。実際に、本人の立場ではどんな状態を体験するのか、モデルを以下に示します。
健康な人の神経は、その時、その場面で必要な情報を選択する働きをもっています。例えば、騒がしい宴会場で近くにいる人と会話をする場面を想像してみてください。実際には周囲の様々な雑音も、会話中の相手の声も、同時に耳の中に入ってきています。ところが、まるでフィルターのように、脳の神経には必要な情報と必要でない情報を分けて伝える働きがあり、そのために健康な場合は、会話中の相手の話に集中することができるのです。
こうしたフィルターに穴があき、選択機能が働かなくなると、必要な情報も、そうでないものも一緒くたになり、以前なら気にも止めなかったような周囲の物音に敏感になったり、様々な出来事に特別な意味付けをして不安に陥ったりするようになってしまいます。
したがって、急性期などの時期に見られる本人の引きこもりは、むしろこのような情報の氾濫から身を守るための工夫であるとも考えられるのです。
薬物療法によって過敏になりすぎた神経が本来の状態に回復すると、フィルターの働きも回復するのです。
開いてみよう
2-5.総合失調症は治るのですか?
「統合失調症が進行性の病気である」という誤った仮説が19世紀末に唱えられ、長年にわたって信じられてきました。しかし、20世紀後半以降に様々な研究が行われ、統合失調症が進行性の病気とは言えないこと、再発する可能性はあるが多種多様の経過をたどり完全に回復する例も多いこと、経過が長くなるとかえって症状が安定する人が多いことなどの結論が得られています。
発症後40年までの経過を見ると、3分の1から3分の2の人が、自立しているかまたは誰かの力を借りながら社会生活を送っていることを複数の研究が示しています。
また、現在、約20万人が精神病院に入院していますが、社会的な環境が整えば退院できる人が多くいるといわれています。今後、薬物療法やリハビリテーションの進歩、地域生活支援システムの充実により、地域で生活できる人がさらに増えると考えられます。
2-6.進学、仕事、結婚は大丈夫ですか?
もちろん個人差はありますが、この病気にかかってから大学に進学したり、結婚する人もいます。発症する前に就いていた仕事を継続している人も少なくありません。
そのためには本人が病気と治療の必要性についての理解を深め、再発をしないよう工夫することが大切です。また、急性期症状が回復した後は焦らず、ゆっくり休める環境に身をおき、徐々に元の生活に戻っていくことがポイントになります。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.




